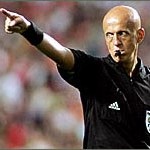お父さんコーチには頭がさがります。
私は男の子がおらず、子供たちはサッカーをしなかったので、コーチとして自分の子供がいるところをタッチすることはありませんでした。
その代わりと言ってはなんですが、少年カテゴリだけではなく、社会人や中学、高校年代の監督やコーチを経験させていただけるチャンスをいただき、今も審判とプレーヤーをやりながらもコーチをする環境をいただいています。
◇
練習のために家庭も仕事も放りだしてやっている人もいますし(もちろん家庭が理解してもらっているからできるのです)、平日練習や土日にきっちり休むために練習のない日に鬼のような残業をこなし、平日の会議が長引けばいらいらして「練習が始まってしまう」なんてプレッシャーをもってやっておられることでしょう。
そこまで人生に打ち込むことができることとは素晴らしいことだと思っています。
だからこそ、真剣に自分がどうあるべきなのかを考えてほしいと思うのです。
◇
お父さんコーチの多くは「無償ボランティア」です。
基本「有償」でしか動くことのない私には、本当にすごいことだと思っています。
しかし、その無償と有償の違いは大きなものがあるのですが、それがどうこうとは言いません。
お父さんコーチは、小学校などであれば子供がお世話になっている間、コーチをするという方が大半です。
運営のために打合せ(飲み会もしょっちゅうですが(笑))をし、審判をやり、奥さんから家事をしないと文句を言われ、それでも子供がいるからとグラウンドに足を運んでコーチとして立っています。
そういう方が多くいるのはよくわかりますし、本当に頑張っているのだなと思います。
◇
ところがそういうお父さんコーチの多くに「息子のいる学年しか興味がない」「強くなる意味が分からない」「サッカー経験がないから審判なんかできっこない」ということを発言する人がいます。
クラブとしてどうするのかという違いはあると思います。
無償ボランティアとしての限界で、クラブの指導はここまでしかできないというのは理解します。
だからスーパー小学生はより強いクラブに移籍したりします。
ですがそんなことがあっても町クラブはそういう無償ボランティアの方に支えられて動いているのが事実です。
そのため、クラブとしてできる範囲があるのはその通りだと思いますし、その中でクラブをどういう方向に持っていくのかというのは、それぞれのクラブの中に共通のものを持っていると感じています。
◇
私がお世話になっている台東区でもブルーファイターズというクラブチームがあります。
ボランティアに支えられておりますが、東京都のTリーグでは1ブロックでも上位を獲得しており、東京都U-12も狙えるような位置にいます。
このチーム出身で、昨年ニュースにもなったのは柏レイソルユースからハンブルガーSVに移籍をした伊藤達哉くん、東京ヴェルディユースからトップへの昇格が決まった郡大夢くんがいます。
彼らを快く送り出したコーチたちを知っていますが、今も彼らが帰ってきたときに優しく迎え入れてくれています。
私はそういう立場にいないため、移籍をした選手への興味は半減以下となってしまいますが、ブルーファイターズのお父さんコーチたちはプリンスリーグでの活躍に目を細め、その活躍を応援しています。
こういうところでも、お父さんコーチの懐の深さは素晴らしいものだと思っています。
◇
こういう人たちも多くいるのは知っていますし、私は彼らをリスペクトしています。
しかしながら、決してそういう人ばかりではないというのもまた事実です。
先ほども書きましたが、自分の息子の学年しか興味がなかったり、なぜサッカーをやるのかという意義を見出さず、ただこなしているというのは本当に子供たちにとっていいのか?という疑問がわいてくるのです。
実例ですが、お父さんコーチの息子の学年を監督していて、彼は息子をずっと試合に出し続けるということがあったそうです(その逆もあるようですが・・・)。
それが突出したプレーヤーであったとしても、同じ学年の保護者からは文句が出たり、快く思われていなかったり、陰口をたたかれるということが往々にしてあるようです。
さらにその監督は息子の卒業とともにコーチもやめてしまい、今では全く協力をしないので余計に陰口をたたかれているという人を実際に知っています。
(言っておきますが、ブルーファイターズじゃないからブルファイのコーチは気にしないでよ!(苦笑))
私のように二十歳からコーチをやっていて、当然ながら息子もいない中で監督をしていても、保護者とはすごく無責任なもので自分の子供にしか興味がない人というのをたくさん見てきました。
起用法に文句を言ってくる人もいましたし、出場時間が他の子よりも1分少ないなんてクレームを受けたこともあります。
私がコーチをする時のスタンスは、基本的に全員を出したいと思っていながら、しかし「この試合に勝てばカテゴリが変わる」というような試合には選手起用が偏ることがあるというものです。
プロフェッショナルなコーチではないため、その戦績でボーナスが出るとか報酬が変わるとかはありませんが、選手たちにもう一つ上の景色を見せたいというのは絶えず思っていますから、そういう起用法になるのはやむを得ないと私は考えています。
それが私自身もすべてではないと思っていますし、チームの底上げこそがそのクラブにとって良いものになるのであれば、絶えず平均的に起用するなどでもいいと考えています。
ですから、それぞれのコーチ(お父さんコーチだけではなくて)は本気で悩んでいるはずです。
◇
少しお父さんコーチからはずれてしまいました。
とまあ、特に小学生チームではこういう環境や議論の中でお父さんコーチが多く活躍されています。
その中から素晴らしいプレーヤーが生まれてきているのは事実で、そこから別のクラブを経由して台東の二名のような選手もでてきたりします。
これが事実でありすべてだと思っています。
だからこそ審判のところでも述べましたが、グラスルーツこそ大事だと思っているのです。
たまに「D級指導者を取る意味が分からない」とかいう人の意見を聞くこともありますが、私はC級を受験した際に「人の教え」なり「JFAの指導要領」を考える機会に接し、何をしたらいいのかというのを整理することができました。
ですからコーチとして30年以上サッカーと接している中で、まだまだ学ぶべきものはありますし、時代によって変わっていくものも多くあるために、常に学ぶ姿勢というのが必要になります。
もちろん仕事や家庭で忙しくて、それらを犠牲にしてグラウンドに立っているお父さんコーチにも、そういう学びをするべきだと思っているのです。
◇
審判は競技規則にかかれているものを施行するためにいるので、その範囲というのが明確に決まっています。
しかし、指導というのは指針はあったとしても、明確に何をすればいいのかというのはどこにも書かれていません。
共通だと思うのは選手を楽しませることだということだけだと思っています。
巧くするなんてのは、その先におまけのようについていることなのですが、そこに持っていくためにどうするのか、巧くなったら今度はその先をどうするのか、ずっと考えることがあります。
もう一度最初に戻りますが、本当にお父さんコーチたちには頭がさがります。
だからこそ、自分が真剣にどう取り組んでいるのかを考えていただきたいと願っています。
努力をなさっているお父さんコーチをリスペクトするからこそ、敢えて文章にしてみました。
もし、問題があるような点がありましたら、コメントやメッセージでいただけると幸いです。