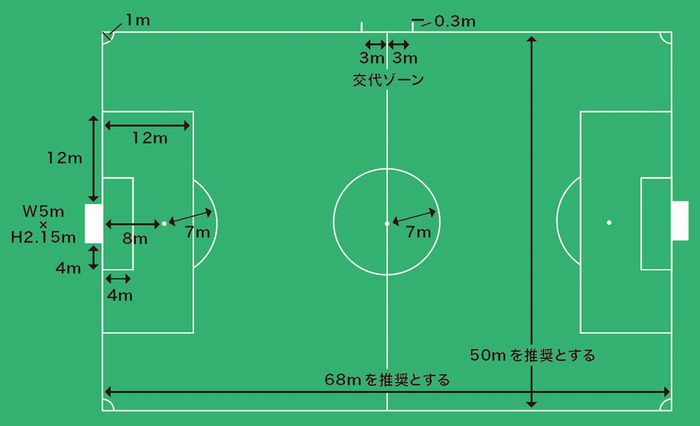サッカーにおいて走るということは、間違いなく必要な要素です。
その間違いない要素に対して、当然ながらレフェリーは「走る」ということになります。
今は横の動きだけだと思われている副審ですが、これがかなりダッシュも多く、しかも自分の意志とは関係なくラインの前後についていかねばならないため、かなり厳しい動きになります。
しかし、やはりたいへんなのはレフェリーで、90分ゲームですと12kmくらいをダッシュも含めて行った上に、ジャッジもしなければならないというのは、なんの拷問だ?とある人から言われたことです(苦笑)
私たちが担当する試合もそうですが、グラスルーツであったとしても間違いなく必要で、それこそ年齢が低ければ低いほど、私は走ることが必要であり、さらに近くで見てあげることが必要だと思っています。

◇
私が審判をやっている理由で書きましたが、私はある審判の姿を見てこれではいけないと思ったからこそやっています。
センターサークル付近からどうやったらペナルティエリアの細かいファウルがわかるのか?という疑問が当然ながら選手も思うでしょうし、先日私がゴールキーパーとしてイエローカードをもらったシーン(PKになりましたし)でも、ゴール裏にいた方から「ノーファウルに見えた」と言うのですが、完全に遅れて入ってきたレフェリーはPKでイエローカードという二重の苦痛を味わいました^^;
とまあ、それはおいといて・・・そういう時に走っていない、走らないレフェリーに対して、選手がどう思うのかということです。
きっと私が思ったことと同じようなことを思うのではないでしょうか。
そう考えると、レフェリーはそのプレーがどうであったのか判断するためには、近くに寄るため走らなければなりません。
逆説的に言うと、走ることのできない審判は判定できないわけですから、そこにいてはならないのかもしれません。
◇
アクティブレフェリー研修会では、必ず「体の準備、頭の準備」というのを言われます。
体の準備というのは走ることのできる体力であったりフィジカルのことを言っています。
頭の準備は競技規則や例を頭に入れることですが、やはり体の準備というのはきちんとしておかねばなりません。
そういった意味において、あくまで「私」はということになりますが、納得ができる走りができなくなったら、アクティブレフェリーをやめようと思っています。
小学生の大会などで必死に走っているかもしれませんが、少なくとも今のレベルでのレフェリー活動はしないでしょうし、そこにしがみついているのはナンセンスだと思っています。
その日が一日一日近づいているわけですが、その日が来るまでとにかくまずは走るということをやっていこうと思います。
・・・・・当然、頭の準備もしたうえでということにはなりますが・・・(笑)