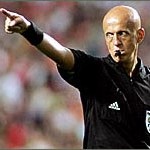公式戦にはレフェリーが最低一人必要になります。
少年で8人制の場合にはレフェリーのみ、それ以外ではアシスタントレフェリーを2名任命することができます(できますというのは競技規則の第6条副審の最初に書いてあるからです)。
そしてそのレフェリーの権限とは試合の結果を含めて最終決定となります。
実はレフェリーとはそれくらい重い決定権を持っていることになるわけです。
◇
では、保護者の方がお子さんの公式戦の試合を見ていて、「なんだよあの審判!」と思ったことはありますか?
ほとんどの方がきっとあると思います。
その程度の大小はさまざまあるかもしれませんが、自分の子供のチームに不利な笛を吹かれたときに、きっと同じようなことを思うことでしょう。
しかし、審判を守る立場から言えば、主審の権限とは大きいことと、それを背負うという責任があるため、かなり大変なことになるのです。
ですからもしそのジャッジに対して「なんだよ!」と思ったとしても、それをぐっとこらえて「選手たちのために頑張っているんだ」と考えてください。
◇
しかし審判のみなさんにも覚えておいていただきたいことがあります。
きっとさまざまな理由でそこにいるのだという事情はお察しいたします。
お父さんコーチで人がいないので仕方がなく立っている方もいるでしょう。
若手で審判の経験を積みたいがために立っている方もいるでしょう。
そして、もしかしたら周りから審判活動が好きだと思われて、実は好きではなく使命感で立っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
(といいながら、それを楽しみ始めている私のような者もいます)
どんな理由で主審になったのかは問いません。
目の前の試合に精いっぱい取り組んでください。
そして、その試合を見ている人はいるのだということを覚えておいてください。
例えば服装や姿勢です。
選手がびしっと直立しているというのに、審判がだらしがなく挨拶をしてみたり、ショーツのひもを外側に出してぶらぶらさせてみたり、襟も互い違いでだらしがなく見えたとして、それを選手だけではなく選手の保護者やベンチの監督やコーチも見ています。
そのレフェリーが素晴らしいジャッジをしたとしても、たいていの人はその素晴らしいジャッジよりもだらしがなさの方を記憶してしまいます。
人の記憶であったり思いというのはそういうもので、背筋をピシッと伸ばしてキビキビとジャッジして、たまにミスがあったとしても、「頑張っているんだな」と感じられるような人であれば、ある意味少々のミスは「プロじゃないんだから仕方がない」と思ってくれる人が大多数です。
逆にそれでジャッジも観客の中で合格点であったなら「今日の審判はよかったね」ということになります。
つまりは「姿勢」というのがとても大切だということなのです。
そして、その試合に真剣に取り組んでいましたか?
ジャッジをする時の手をピシッと伸ばしていましたか?
フリーキックの場所を示す時に、ジョグではなくて歩いてやっていませんか?
そこを少しずつ変えてみれば、きっと観客からも選手からも最大のリスペクトをされると思っています。
◇
お父さんコーチの中にも仕方がなくやっている人もいることでしょう。
しかし、あなたの子供がどこかの審判のお世話になっているように、あなたもレフェリーとなった時、そこに選手や監督、コーチ、観客は見ているのです。
そこでクレームをつけられたり、罵声を浴びせられることもあるでしょう。
ですが、それはきっとあなたのジャッジや姿勢が足りないと見られているのです。
そして、そこに「無償ボランティアだから」という甘えは捨ててください。
これはコーチとしてもそうなのですが、有償であれ無償であれ育成にはアマチュアリズムの甘えはできません。
「指導でうちのチームはここまでしかできない」というのはわかりますが、やらねばならないことというのはレフェリーは競技規則で定められているわけですから、その部分は満たしてもらわなくてはなりません。
それだけの責任を指導者としてもレフェリーとしても持っているのです。
そして、その覚悟がないのであれば、私はどうするべきなのかを、チームスタッフと相談して決めてほしいと思っています。