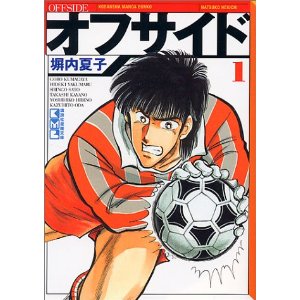東京都のアクティブレフェリーになってからかなりの年数が経っていますが、今年は特に割り当ての多い年だと思っています。
昨年でさえかなり多いと思っていたのですが、今年は昨年一年の割り当て数をもう少しで越してしまいます。
それだけ東京都の審判員が足りないということなのでしょう。
なにせ今年は都学連の3・4部の試合の審判も入らない(貴重な主審経験の場です)くらいですし、平日夜の高校生のTリーグの審判なども割り当てられています。
そんな中で、審判として(主審・副審双方で)全国区の学校の試合などを担当させていただくことがあるのですが、きちんとジャッジをするということも当然なのですが、なによりも争点をできるだけ近くで見るということを心がけています。
そういう試合は強化担当や学連、トレセンの審判が担当することが多いのですが、おっさん審判の中でも「まあ工藤ならなんとかなるだろう」と割り当ててもらえることに感謝をしています。
しかし、それに応えるためには日頃の体調管理というのが重要になってきます。
自分の選手としての練習会では派手な腰痛のため全く走ることができなかったため見事なまでに落とされましたが、審判としてはそうしたミスは選手のために許されるものではありません。
審判にとっては担当している一試合かもしれませんが、選手たちにとってはもしかしたらその後の人生が決まる一試合になるかもしれないのです。
ですから食生活にしても(昨年離婚をしたというのに・・・w)、トレーニングにしても手を抜くことのないように、自己管理が必要なのだと理解して今日も動いています。
このレベルで審判ができるのはあと少しだと思いますが、走ることができるうちは懸命に続けていこうと思います。