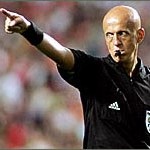現在FC台東U-15のコーチとしてベンチ入りをすることもあるのですが、Tコーチからも言われるとおり普段は前向きな言葉が多いといわれます。
選手を責めることは基本的になく、どうすればよりよいモチベーションで試合に臨み、どうすればゲームを組み立てることができるのかを「考える」ようになってほしいと考えています。
サッカースクールではテクニックの部分も教えることはありますが、基本はアマチュアコーチとは違う気持ちの持って行き方であったり、選手の個性を伸ばすことに注力をしています。
そんな私もベンチに座っているときに冷静でなくなることがあります。
それは審判があまりにもひどい場合となります。
・繰り返し何度もアタックを行う選手に注意さえせず、できるだけカードを出さないようにする
・走らない(走れない)
・選手から離れたところでジャッジを行う(副審が近いのは別)
・副審がオフサイドのルールを知らないで行っている
主にこんな時です。
オフサイドルールに関しては2013年夏の改定でDFがプレーをしたと判断される場合には、オフサイドポジションにいる選手はオフサイドではなくなるとあります。
しかしルール改定から1年半経ってもまだ「知らない」という審判がいるのも事実です。
そして何よりオフサイドそのものを理解していない審判がいます。
攻撃側の選手がパスを出す瞬間に、センターラインを超えてゴールとボールの間に二人以上の選手がいなければならないとなっているわけで、明らかにパスが出た後にディフェンスの裏に抜けているというのにオフサイドのフラッグを上げられることが多々あります。
シニアのゲームでも嫌になるくらいあります。
一試合で四回取られたときは、一度目はあやしいなあと思い、二度目は確信に変わり、三度目は遅れて出て行ったのにあげられ、四度目は明らかに遅れて出て行ったのにオフサイドとされました。
怒る気力さえもなく、呆れに近かったでしょうか。
そんなことを若い年代でやられてはこまるわけです。
選手は理不尽さに対して若ければ若いほどもろいものなのです。
だからこそあまりに酷い審判には声を出すことがあるのです。
私が冷静じゃない時というのは、そういうことなのです。